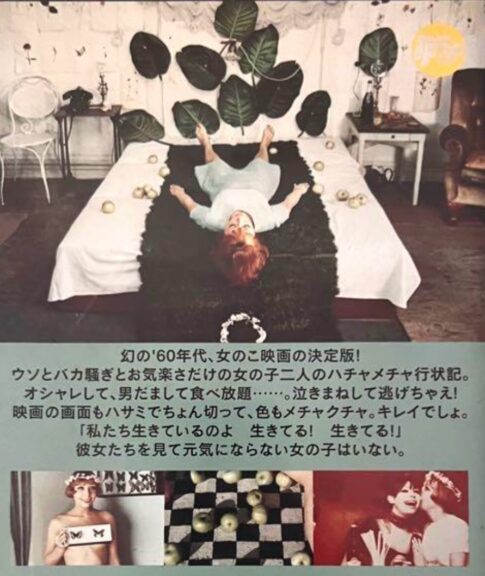こんにちは絵描きのひつじです。

私は普段、半抽象の風景画を描いています。
……といっても、
「半抽象って何?」
と思う方も多いかもしれませんね。
日本では、抽象画よりも具象画(りんごを見てりんごだとわかる絵)の方が圧倒的に人気があります。
美術館でも、印象派やルネサンスの展覧会は大盛況なのに、
抽象画の展示は「よくわからない」と敬遠されがち。
それはとても自然なことだと思います。

抽象表現というのは、何も具体的なものを描いていない絵のこと。
たとえば、ジャクソン・ポロックのように絵の具を垂らして描いたり、
マーク・ロスコのように色の面だけで表現したり、
サイ・トゥオンブリーのように線や落書きのような表現をしたり。
個人的には、ロスコやトゥオンブリーが大好きです。
形がないからこそ、色や線そのものが語りかけてくる感じに引き込まれます。
半抽象は、その間にある表現。
完全に形をなくすのではなく、「何を描いているかはわかるけれど、写実的ではない」絵のことです。
半抽象って、実は「余白」が魅力なんです。
写実画のようにすべてを描き込むのではなく、形を少し崩したり、色を変えたり、輪郭をぼかしたり。
その「完璧じゃない部分」が、見る人の想像を呼び込む余地になる。
「この景色、どこかで見た気がする」
そんなふうに、それぞれの記憶や感情を重ねられるのが、半抽象のいいところです。
目次
半抽象とは?心象風景を描くということ

半抽象というのは、具象と抽象の間にある表現のこと。
海外では「Semi-abstract」と呼ばれたり、「モチーフが内在している抽象表現」と説明されたりします。
完全に形がなくなってしまうわけではなく、
「何を描いているかはわかるけれど、写実的ではない」
「形は残っているけれど、色や線が現実とは違う」
そんな絵のことです。
私が普段描いている風景画も、この半抽象的な表現です。
たとえば、海や森、街並みを描くとき。
「ああ、これは海だな」「木がある風景だな」とわかる程度には形を残しながら、
実際に見た景色というより、心の中に残った印象や感情を描いています。
それは心象風景と呼ばれるもの。目に見える風景ではなく、心の中にある風景。
記憶や感情、光の残像が混ざり合った、内面的な景色です。
夜なのにピンク。心が感じた色を描く

夜の風景を描くときも、私は実際の暗さをそのまま描きません。
夜なのに明るいピンクや、淡い水色を使うことがよくあります。
それは嘘ではなく、心が感じた夜の色。静けさの中にある温かさや、
闇の中に潜んでいる優しさを、色に変えて表現しているのです。
だから、私の風景画は写真のようにリアルではありません。
でも、その「現実から少し離れた感じ」が、私の心が見た景色なのです。
夜空を見上げたとき、真っ黒ではなく、深い青やほんのり紫がかった色を感じることがある。
街灯の光がオレンジに温かく滲んで、
その周りだけやわらかなピンクに見えたりする。
そういう「心が感じた色」を大切にしています。
けれど、時々ふっと「静物画を描きたい」と思う瞬間があります。

果物や花瓶、コップやパン。
身近にある小さなものたちをじっと見つめていると、
風景画とは違う、もっと静かで親密な対話。
ものたちとの、やさしい時間。
そんな気持ちになるとき、私は静物画を描きます。
そして静物画でも、私のアプローチは風景画と同じ。
現実の色をそのまま使うのではなく、
心が感じた色を選びます。
写実から離れるという選択

とはいえ、いわゆる写実主義のように、
細部を完璧に描きたいと思ったことは一度もありません。
学生時代にはデッサンの訓練をさんざんしてきたので、
「描こうと思えば描ける」ことはわかっている。
でも、私が描きたいのは正確さではなく、
ものの中にある“息づき”や”時間”のようなもの。
目に見える形の奥にある、
ふとした光や空気の記憶を留めたくて、筆を取るのだと思います。
技術として「描ける」ことと、
「描きたい」と思うことは、別のことです。
写実的に描く技術があっても、私の心は、もっと別のものを求めている。
それは、完璧に再現された形ではなく、記憶の中で少しずつ変化していく、
やわらかな輪郭や、曖昧な色。
不完全さへのフェチズム

年を重ねるにつれて、
自分の中の”美のフェチズム”がはっきりしてきました。
ピントが外れていたり、ぼやけていたり、
形が少し崩れていたり――
その「不完全さ」にこそ、美しさを感じます。
完璧に描かれた花瓶より、
少し滲んで光を抱きこんでいる輪郭の方が、
生き生きしているように見える。影が強すぎるより、
光が溶けて曖昧になっている方が、そこに”ぬくもり”がある。
そんな風に感じる自分の感覚を大切にして、
特に静物画を描くとき、私はいつも印象派的なまなざしを持って見ています。
写実的な絵が好きな人もいるし、それも素敵なことです。
細密に描かれた絵の美しさも、私はちゃんと理解しているつもりです。
でも私にとって「描く」ということは、
見えているものをそのまま写すことではなく、
心が感じた温度や空気感を形にすることなのです。
カメラで撮ったような正確さより、
記憶の中で少しずつ色褪せたり、逆に鮮やかになったりする、
そのゆらぎの方が、私にとっては真実に近い。
印象派が教えてくれたこと:光と空気を描く

印象派の画家たちは、
「ものの正確な形」ではなく、
「その瞬間の光と空気」を描こうとしました。
モネやルノワールが描いた花や果物は、
よく見ると形がとてもあいまいです。
でも、そこには確かにその場の空気が流れている。
セザンヌのりんごも、よく見ると遠近法が少しおかしかったり、
テーブルが傾いていたりします。
けれど、その「ずれ」があるからこそ、りんごは静止した物体ではなく、
呼吸しているように見えるのです。
目の前のモチーフと、心の中のコラージュ

静物画を描くとき、実際にモチーフを用意することもあります。
テーブルの上にレモンを置いて、陶器の小皿を並べて、
その日の光がどう当たるか観察する。それはそれで、とても豊かな時間です。
目の前にあるものを観察しながら描くと、思いがけない発見があります。
「レモンの影って、こんな色なんだ」
「白い皿に、窓の緑が反射してる」
そんなささやかな驚きが、絵を描く喜びになります。
朝の光と、夕方の光では、
同じモチーフでもまったく違って見える。そういう変化を楽しみながら、
筆を動かす時間が好きです。
空想で組み立てる静物画

けれど、私の場合は「空想で描く」ことも多い。
頭の中で、いくつもの記憶を組み合わせて、
存在しない静物画を作り上げていくのです。
たとえば、
朝食で見たパンの質感と、数日前に見た窓辺の光と、
ずっと昔に触れた布の色を、ひとつの画面に重ねていく。
それはまるで、心の中でモチーフをコラージュしていくような感覚です。

実際には存在しない組み合わせなのに、描き終わったとき、
「ああ、確かにこの風景を見た気がする」という不思議な感覚が残る。
記憶の中のものたちは、時間とともに少しずつ形を変えていきます。
色が鮮やかになったり、輪郭が柔らかくなったり。
だから、空想で描く静物画は、現実よりもやさしく、
どこか夢のような雰囲気になるのかもしれません。
現実には一緒に並ぶことのないものたちが、心の中では同じテーブルの上にある。
それは嘘ではなく、私の内側にある真実の風景なのです。
印象派との違い:見たものと、感じたものの間

印象派の画家たちは、基本的に「目の前の現実」を描きました。
モネは睡蓮の池を何度も描き、ルノワールはカフェにいる人々を描き、ピサロは街の風景を描いた。
彼らは「今、ここにある光」を捉えようとしたのです。

印象派が革新的だったのは、アトリエの中ではなく、屋外で絵を描いたこと。
刻一刻と変わる光を、その場で捉えようとしました。
だから、印象派の絵には「瞬間」が閉じ込められています。
ここが、印象派と私の描き方の大きな違いかもしれません。
心の中の光を描く

私は、必ずしも「今、ここ」を描いているわけではない。
記憶の断片や、見たことのないはずの光景が、
筆を動かすうちに浮かび上がってくる。
それは現実とも夢ともつかない、でもどこか懐かしい風景。
誰かの部屋かもしれないし、
私がまだ訪れていない場所かもしれない。
印象派が「外の世界の光」を描いたとすれば、
私は「心の中の光」を描いているのかもしれません。
だから、モチーフがリアルである必要はないのです。
現実にないものを描くことに、抵抗を感じる人もいるかもしれません。
「それって嘘じゃないの?」と。でも、心が感じたことは、決して嘘ではありません。
むしろ、目に見えるものだけが真実ではないのだと、
絵を描くたびに思うのです。
まとめ
半抽象の心象風景には、余白がある。私が描いているのは、自分の心の中にある風景。
でも不思議なことに、それを見た人が「懐かしい」と言ってくれることがある。
なぜだろう。
きっと、抽象の余白が、見る人の記憶とリンクするからだと思う。
私の夜空のピンクが、誰かの記憶の中の夕暮れと重なる。
私の曖昧な輪郭が、誰かの忘れかけていた景色を呼び起こす。
心象風景は、私だけのものじゃない。
描いた瞬間から、見てくれた人の心象風景にもなっていく。
それが、半抽象で描く意味なのかもしれない。
個人的な記憶が、余白を通して、誰かとつながっていく。そんな気がしています。
今日は、ひつじの美のフェチズムのお話でした。
また次回、絵のこと、色のこと、お話しできたら嬉しいです。
それでは、またお会いしましょう。