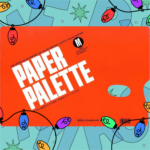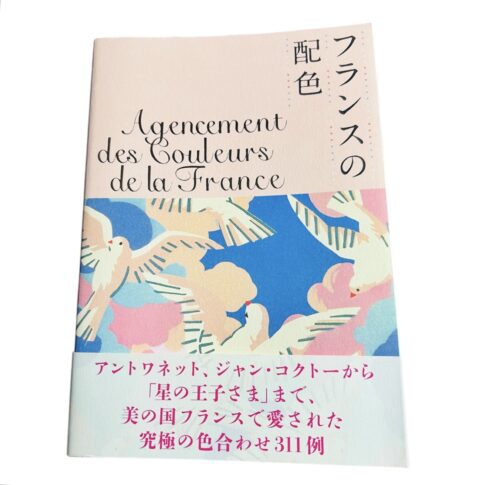こんにちは 絵描きのひつじです!
皆さん、普段絵を描いているときに、
思い通りの色が作れず、濁ってしまった経験はありませんか?
「絵の具が悪いのかな?」
と思ったことがあるかもしれませんが、実はその原因は色の仕組みを知らなかったことかもしれません。
今回の記事では、色作りの鍵となる
「カラーバイアス(隠れた色)」の考え方を基に、
混色の秘訣を解説します。失敗例と成功例を交えながら、あなたの混色スキルをアップデートしましょう!
色相環とは?基本から解説

**色相環(カラーホイール)**とは、色を円形に並べたものです。これにより、色同士の関係性がひと目でわかります。
• 原色(赤・青・黄)
色相環の基盤となる3つの色。この3色を混ぜることで、すべての色が作られるとされています。
• 二次色(橙・緑・紫)
原色同士を混ぜた色。たとえば、赤+青で紫、青+黄で緑が作られます。
• 補色(色相環で正反対の位置にある色)
赤と緑、青と橙など、補色同士を混ぜると色が濁る特性があります。
この色相環を理解しておくことは、絵を描くうえでの基本です。でも、これだけでは「なぜ茶色や濁った色になるのか」の説明は不十分。そこで登場するのがカラーバイアスです。
カラーバイアスってなに?

色の「隠れた性質」を知ろう
カラーバイアスとは、絵の具や顔料が「どの方向に色が偏っているか」を表す性質です。
同じ「青」でも、赤寄り(暖かい青)や
緑寄り(冷たい青)があります。この偏りを知らずに色を混ぜると、くすんだ色や濁った色になりがちです。
なぜ色混ぜがうまくいかないのか?

子供の頃、多くの人が絵を始めたとき、
学校で黄+青=緑、赤+青=紫と教わります。
でも、どの黄+青、赤+青で混ぜるかで結果が大きく変わることは説明されません。
失敗例

カラーバイアスに関する失敗例をいくつか挙げてみます。これらは、色作りにおいて誤った選択がどのように影響するかを説明します。
「濁った紫」になる失敗
間違った組み合わせ:
• 赤:カドミウムレッド(オレンジ寄り)
• 青:ウルトラマリンブルー(紫寄り)
結果:
紫を作ろうとすると、カドミウムレッドに含まれるオレンジ寄りの色素が、補色(青に対する補色はオレンジ)の役割を果たし、混ぜた色が濁ってしまう。鮮やかな紫にはならない。
解決策:
紫寄りの赤(マゼンタやクリムゾンレッド)を選ぶと、鮮やかな紫が作れる。
「灰色がかったオレンジ」になる失敗
間違った組み合わせ:
• 赤:アリザリンクリムゾン(紫寄り)
• 黄色:レモンイエロー(緑寄り)
結果:
赤と黄色を混ぜて鮮やかなオレンジを作りたかったのに、紫寄りの赤と緑寄りの黄色が補色に近い関係になり、混ぜた色がくすんでしまう。
解決策:
オレンジ寄りの赤(カドミウムレッド)と黄色(カドミウムイエロー)を使うと、鮮やかなオレンジが作れる。
「くすんだピンク」になる失敗
間違った組み合わせ:
• 赤:カドミウムレッド(オレンジ寄り)
• 白:チタニウムホワイト
結果:
鮮やかなピンクを作ろうとしても、カドミウムレッドのオレンジ寄りのバイアスが影響して、くすんだサーモンピンクになり、クリアなピンクにはならない。
解決策:
マゼンタのような紫寄りの赤を使うと、クリアで鮮やかなピンクが作れる。
「くすんだ緑」になる失敗
間違った組み合わせ:
• 青:ウルトラマリンブルー(紫寄り)
• 黄色:カドミウムイエロー(オレンジ寄り)
結果:
鮮やかな緑を作ろうとしても、紫寄りの青とオレンジ寄りの黄色の補色成分がぶつかり、くすんだ緑になる。
解決策:
緑寄りの青(フタロブルー)と緑寄りの黄色(ハンザイエロー)を使うと鮮やかな緑が作れる。
失敗を避けるポイント
• 使用する絵の具の「カラーバイアス(色の偏り)」を理解する。
• 混色する際は「混ぜたときの補色成分」に注意する。
• できるだけ色の成分がシンプルな絵の具(単一顔料のもの)を使う。
成功例
カラーバイアスをうまく活用した成功例を挙げてみます!これらは、鮮やかな色や理想的なニュアンスの色を作るための具体例です。
鮮やかな紫を作る成功例

正しい組み合わせ:
• 赤:アリザリンクリムゾン(紫寄り)
• 青:ウルトラマリンブルー(紫寄り)
結果:
どちらの色も紫に偏っているため、混ぜたときに補色成分が少なくなり、深くて鮮やかな紫を作ることができる。
用途:
夜空の背景や花びら(スミレ、ラベンダーなど)の色に最適。
明るいオレンジを作る成功例

正しい組み合わせ:
• 赤:カドミウムレッド(オレンジ寄り)
• 黄色:カドミウムイエロー(オレンジ寄り)
結果:
どちらもオレンジ寄りのバイアスを持つため、補色成分が抑えられ、鮮やかで純粋なオレンジが作れる。
用途:
太陽や夕焼け、秋の葉の色合いに使える。
鮮やかな緑を作る成功例

正しい組み合わせ:
• 青:フタロブルー(緑寄り)
• 黄色:ハンザイエロー(緑寄り)
結果:
緑に偏った青と黄色を混ぜることで、明るく鮮やかな緑を作ることができる。
用途:
新緑の木々、草原、エメラルドグリーンの海などにぴったり。
クリアなピンクを作る成功例

正しい組み合わせ:
• 赤:マゼンタ(紫寄り)
• 白:チタニウムホワイト
結果:
紫寄りの赤に白を混ぜることで、濁りのない鮮やかなピンクを作ることができる。
用途:
桜の花びらやキャンディの色合いに適している。
柔らかいターコイズブルーを作る成功例

正しい組み合わせ:
• 青:セルリアンブルー(緑寄り)
• 緑:フタログリーン(青寄り)
• 白:少量のチタニウムホワイト
結果:
セルリアンブルーの緑寄りのバイアスがターコイズブルーを際立たせ、白を少し混ぜることで柔らかいニュアンスが生まれる。
用途:
海の表現や空の淡い部分に最適。
深いネイビーを作る成功例

正しい組み合わせ:
• 青:ウルトラマリンブルー(紫寄り)
• 黒:ランプブラック
• 赤:ほんの少しアリザリンクリムゾン(紫寄り)
結果:
青に紫寄りの赤を足すことで深みが増し、黒を少量混ぜると暗いネイビーが完成する。
用途:
夜景や影の表現にぴったり。
ポイント:成功するコツ
1. 絵の具のカラーバイアス(色の偏り)を意識して選ぶ。
2. 使う色の補色成分を避けるようにする。
3. 実験的に少量ずつ混ぜて、理想的な色を探す。
成功例を参考にすれば、色作りのスキルがさらに磨かれます!

色相環の選び方とカラーバイアスの重要性
カラーバイアスを理解した上で、
色相環をどう使いこなすかが非常に大切です。色相環は色同士の関係性を視覚的に理解するための強力なツールですが、
絵画で成功するためにはその「偏り」を意識して色を選ぶことが重要です。
青でも「赤寄り」のものと「緑寄り」のものがあり、
それぞれ混ぜたときの結果が異なります。そのため、色相環の図を目につくところに置いておくと、色を選ぶ際にすぐに活用できて便利です。

また、色は単に物理的に混ぜるだけではなく、それぞれの色が持つ個性を活かして選んでいくことも絵画の世界では大きな意味を持ちます。
まとめ
失敗は避けられないものですが、
それこそが成長への大切なステップだと感じます。
私自身も失敗を繰り返してきましたが、そのたびに新しい発見や気づきを得ることができました。特に色を扱う際は、実験と試行錯誤が欠かせません。今回は鮮やかな色を作りたいのに濁ってしまう悩み解決にフォーカスした内容でした。いかがだったでしょうか?
カラーバイアスに注目して色を混ぜることで、
イメージ通りの色が作れるようになるとおもいます。失敗を恐れず、色と向き合い続けることで、新しい発見がたくさん待っていることでしょう!
それではまたお会いしましょう。ひつじでした。